ブログ
不動産登記相続人に未成年者がいる場合の相続手続について

目次
いつもお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は未成年者が絡む相続手続のお話しについてです。
案件的にそんなに多くはないでしょうが、極端に珍しいことでもないと思います。
実際、司法書士九九法務事務所でも、なんだかんだ毎年1~2件は携わらせていただいているような気がします。
それなりに注意点の多い手続ですので、改めてご紹介させていただこうかと…
尚、案件によっても、管轄する家庭裁判所によっても、多少なりとも異なる点があると思いますので、諸々の流れや必要書類等については、あくまで参考程度に捉えていただけると幸いです。
未成年者が行う法律行為について

まずは未成年者についてのおさらいを少し。
2022年4月1日、民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
ここ数年、成人式のニュース等で頻繁に報じられていたので、だいぶ世間的にも定着してきたのではないでしょうか?
ちなみに、法律上、未成年者は成人に比べて行為能力が十分でないと考えられています。
結果、契約等、多くの法律行為に制限がかかってしまうわけです。
社会経験や知識の少なさから生じる不利益から、未成年者を守るという趣旨ですねいわゆる。
とは言え、未成年者が行った契約等は絶対的に無効というわけではありません。
契約等を行うには、親権者または未成年後見人(以下、「法定代理人」と表記します。)がその契約に同意することが必要なだけです。
また、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約等は、取り消すことができます。
これを「未成年者取消権」と言います。
単独で行った未成年者の法律行為は、取り消しの対象になるだけであり、後に法定代理人が追認した場合は有効になるわけです。
まあ、この辺りを詳しく論じていると、それだけで一つのブログになってしまうので、そろそろ本題に入ることにします。
(需要があればそのうちに別のブログ記事にでもしてみようかと…)
単独で法律行為ができない未成年者ですが、各種登記や裁判行為を行う場合には、どのような手続が必要なのでしょうか―
また、それに伴う注意点とは―
未成年者は単独で登記申請が出来るのか?

シンプルなようで複雑な問題です。
既述のとおり、未成年者が独力で行った契約行為は取り消しの対象となります。
諸々のメリット・デメリットを判断する行為能力が不足するとされているからです。
では、法務局に対して行う登記申請行為自体は?
これを法律行為と捉えるのでしょうか??
ここでわりと有名な判例をご紹介します。
「登記申請行為は、登記所に対して登記を要求する公法上の権利であって、民法の法律行為ではなく、既に効力の生じた権利変動の公示を求めるものであるから、債務の履行に準じた行為である。したがって、法定代理人の同意がなくとも、未成年者による登記申請行為は、意思能力があれば認めても差し支えないものと解している(最判昭43.3.8判時515・59)
まあ、ようするに出来るのです。
未成年者であろうと、単独で登記申請自体は可能だと(もちろん、意思能力は必須なので、その点はご注意を。)。
小難しく書いてありますが、この内容でも何となく伝わるでしょうし、細かく論じても長くなるだけなので割愛しちゃいます。
登記申請自体は、意思能力のある未成年者なら実質可能と―
ただし、あくまで可能なのは登記申請そのものです。
ここがとても大事ですね。
例えば、司法書士が未成年者から登記の依頼を直接受けられるのかというと…
この点、色々な論議がありそうな気がしますが、私的には難しいと思っています。
登記申請自体については上記のとおり(民法上の法律行為ではない)かもしれませんが、登記の依頼はあくまで「委任契約」ですから。
委任契約は、れっきとした法律行為です。
民法にも定められております。
では、未成年者が司法書士に登記を依頼するにはどうすればいいのでしょうか?
もちろん、方法はあります。
できないと困りますしね。
この点についてだけであれば、そこまで難しい話ではありません。
他の法律行為と同様に考えるだけです。
いわゆる、単に親権者が未成年者の法定代理人として司法書士に手続を依頼し、目的を達成すればいいだけなのです。
ただし―
相続等、一部の手続では親権者が法定代理人になれない事態が生じ得るのです。
この辺りがなかなか分かり難く、かつ、本ブログの本題となるわけです。
未成年者の絡む相続で特別代理人が必要なケースと不要なケース

既述のとおり、未成年者が相続人となる場合は、親権者が代理して手続きを進めるのが一般的です。
しかしながら、親権者と未成年者の利益が対立する(利益相反する)場合には、家庭裁判所に特別代理人という者を選任してもらう必要があるのです。
ようするに常に親権者が代理するわけではないと…
では、どのような場合に親権者と未成年者の利益が対立する(利益相反する)のでしょうか?
簡単ケースを挙げで検証してみましょう。
特別代理人の選任が必要な(利益相反に該当する)ケース
(1)親権者と未成年者が遺産分割協議を行う場合
親権者と未成年者が共に遺産分割協議を行う場合は、利益相反行為に該当することになります。
協議の当事者同士ですから、親権者と未成年者の利害が対立する恐れがあるという考え方です。
また、この辺が混乱する要因になりやすいのですが、仮に未成年者に有利な内容の遺産分割協議であった場合はどうなるのでしょうか?
一見、特別代理人は不要なようにも思えます。
なにせ未成年者に不利益はなさそうですから。
結論からすると―
未成年者に有利な内容であっても、利益相反の構造がある以上、特別代理人の選任が必須となります。
おそらくは、利害が対立する恐れのある法律行為を親権者に代理させない点に重きを置いたものなのでしょう。
納得いかない人も多くいると思いますが、私的にもこれで良いと思います。
そもそも有利か不利かの判断は困難なこともありますし、細かい詳細を論議するよりも、構造そのもので判断した方がトラブルは生じにくいと思うので…
(2)親権者と未成年者が相続人であり、かつ、未成年者のみが相続放棄を行う場合
相続発生後、家庭裁判所での相続放棄手続きについても、親権者が未成年者を代理して行うことになります。
相続放棄は、高度な判断力が求められるため、未成年者は単独で手続きを行うことができないという趣旨ですね。
おそらくこの辺りはそんなに疑義はないでしょう―
では、親権者は相続し(相続放棄をせず)、未成年者のみの相続放棄手続きをする場合はどうでしょう?
これは利益相反に該当し、特別代理人の選任を要します。
親権者が自分の利益を優先している可能性があるという考え方です。
尚、これは遺産内容を問いません。
仮に負債の方が多い相続内容であっても結論は変わりません。
上記同様、構造上、利益相反に該当する恐れがある以上、特別代理人の選任を要するという趣旨ですね。
特別代理人の選任が不要な(利益相反に該当しない)ケース
(1)法定相続による相続の場合(遺産分割協議が不要な場合)
あくまで遺産分割協議を親権者と未成年者が共に行う場合が該当するのであって、相続手続きそのものが問題視されるわけではないのです。
そのため、法定相続は元より、親権者が相続人にはならず、未成年者が代襲相続人になる場合なども同様の帰結となります。
仮に親権者と未成年者が不動産等を共有することに問題がなく、特別代理人の選任手続が面倒等の事情があるならば、『法定相続』を検討するのも一つの手段なのです。
ただし、置かれている状況によってはそれが最適解とは言えないケースもございますので、最終的な判断は専門家とよくご相談ください。
(2)親権者と未成年者が共に相続放棄を行う場合
この場合も利益相反には該当しません。
あくまで親権者が相続し、未成年者のみが相続放棄を行う場合に該当するのです。
特別代理人の役割や注意点について
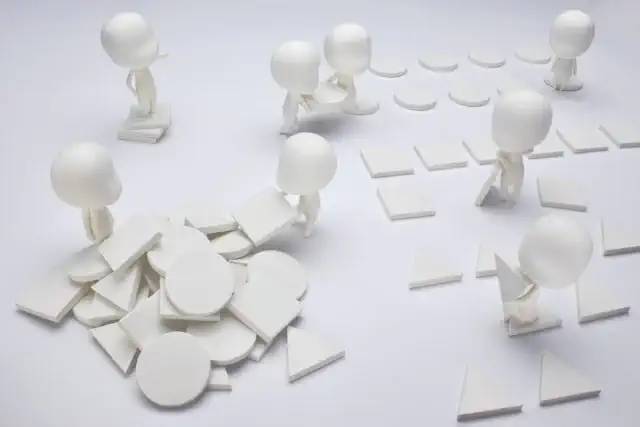
特別代理人の役割はシンプルです。
未成年者の利益を守りつつ、その代理として特定の法律行為を行うこと。
これに尽きます。
そのため、相続の場合等は、原則、未成年者に不利な内容の遺産分割協議は認められません。
最低限、未成年者の法定相続分を確保するというのが前提となるわけです。
ただし、だからと言って、絶対に認められないわけでもありません。
それ相応の事情等を疎明し、家庭裁判所に認められさえすれば、形式上、未成年者に不利な遺産分割協議内容であっても実現できることもあるのです。
尚、それも未成年者の年齢や遺産のバランス等によっても変わってきます。
要は形式上、未成年者に不利な内容であっても、実質的には不利にならないことを疎明すればいいわけです。
僕に当該手続きを依頼いただければ、絶対、大丈夫というわけではありませんので、その点は勘違いしないでくださいね。
理想とする内容で認められたこともありますし、残念ながら遺産分割内容の修正を指示されたこともあります。
大事なことは、あくまで未成年者の存在を無視せず、相続人にとっての最適解を見付けていくことなのです。
特別代理人になれるのは?
特に細かい制限はありません。
もちろん、未成年者や利益相反の当事者は、特別代理人にはなれません。
じゃないと、制度の意味がないですからね。
裁判所に特別代理人の選任を頼むこともできますが、司法書士九九法務事務所では、ご親族に就任してもらうケースが多いと言えます。
父母いずれかの両親や兄弟姉妹等です。
特別代理人を選任するには具体的に何をすればいいのか?~照会書(回答書)についても~
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の選任申立手続きを行います。
申立人は利害関係人です。
尚、利害関係人とは、親権者や後見人、相続人等が該当します。
続いて申立てに必要となる書類についてです。
もちろん、事案によっても異なりますが、一般的には以下のような書類を要求されます。
-
特別代理人選任申立書
-
申立人・未成年者の戸籍謄本
-
利害関係を証する資料(遺産分割協議書案、契約書案など)
-
収入印紙(800円程度)+郵便切手(各家庭裁判所指定)
その後、『照会書(回答書)』のようなものが家庭裁判所から送付されてきます。
それに適した回答を行えば後は選任決定を待つばかりです。
ちなみに家庭裁判所に出頭することは稀です(あるのかな?)。
少なくとも僕が関わってきた案件では一度もありませんでした。
出頭しない代わりに、照会書(回答書)で諸々の確認を行うわけです。
そのため、この回答がとても大事だったりします。
尚、照会書(回答書)は申立人もそうですが、特別代理人の候補者を立てている場合は候補者にも送付されてきます。
また、未成年者自身に送付されることもあります。
明確な規定があるのかどうかは分かりませんが、15歳以上の未成年者には照会書(回答書)が送付される可能性もあると…
現に僕自身、一度、関わらさせていただいた案件で経験させていただきました(お恥ずかしながら当時は未成年者には照会書(回答書)が送付されないと思い込んでいたので、びっくりした記憶があります。)。
また、照会書(回答書)の内容は事案ごとに異なります。
そのため、一概にどういうものかを表現するのは困難です。
ただし、趣旨としては、とにかく未成年者の利益を保護し、適正な法律行為かどうかを判断するためのものなので、一般的には候補者と未成年者との利害関係の有無や、対象となる法律行為が未成年者にとって不利益にならないか等の質問項目が記載されてることが多いでしょう。
もちろん、手続きをご依頼いただいている案件につきましては、最大限フォロー致しますので、その点はご安心ください。
まとめ
今回は未成年者が絡む相続手続きについてでした。
通常の相続手続きより、一気に複雑になるんですよね。
かかる時間も手間も増えてしまいますし、ケースによっては思い通りにならないようなことも…
まずは詳細をご相談いただければと思います。
それでは今回はこの辺で。
write by 司法書士尾形壮一
